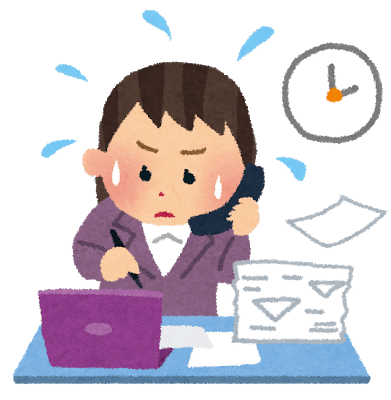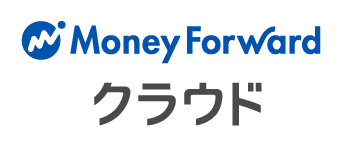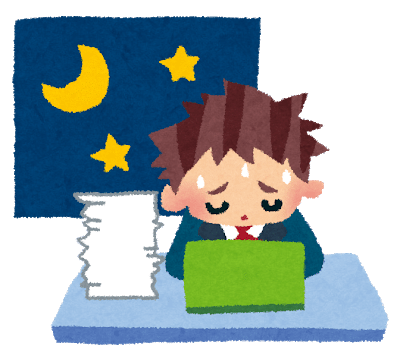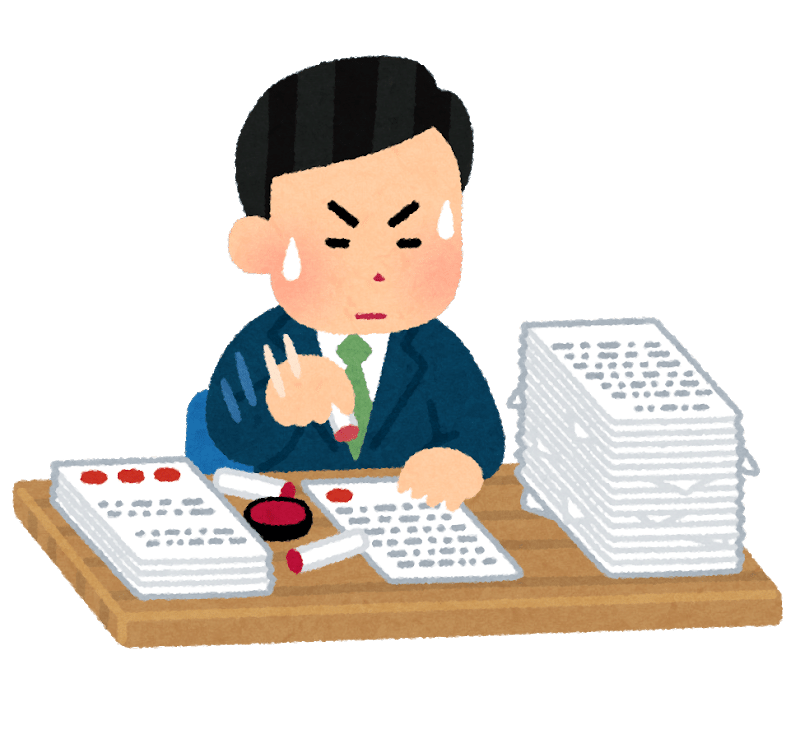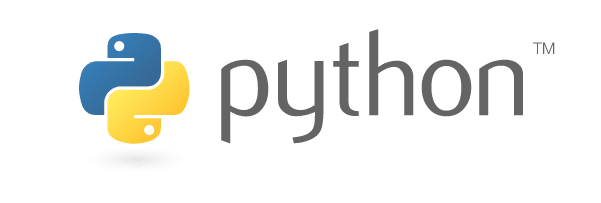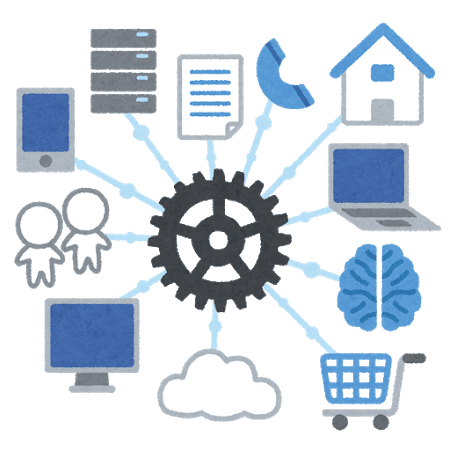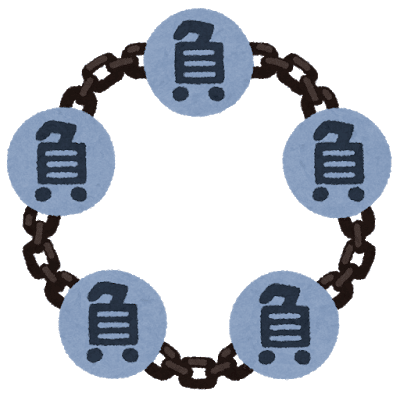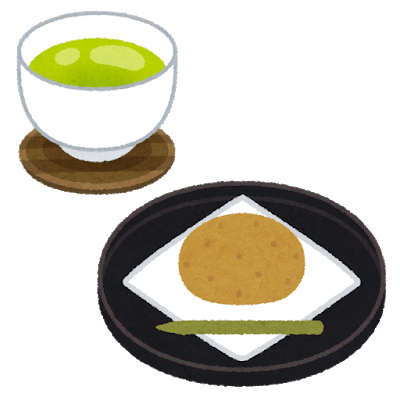ブログ
理念
脇坂IT税理士事務所の理念

皆さん、こんにちは。脇坂IT税理士事務所という者です。
2021年4月に、税理士として独立しました!平成元年生まれなので、業界では若手です(多分)
主に、下記3つの理念を持ち、社会貢献したいと考えております。
・経理(バックオフィス)を強化
・ペーパレス社会の実現
・プログラミング(Python)による効率化
具体的な事業内容につきましては、弊社ホームページをご確認くださいませ。
ここでは、上記⬆️理念の詳細について書きたいと思っております。
興味を持っていただければ、幸いです。
1.経理におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション化)について
経理におけるDX化の具体的な意味につきましては、下記の目標を達成することです。
・経理における単純作業をなくす
・経理が完全に在宅、リモートワークで仕事が完結する仕組みを構築する
この2つに尽きます。順序を追って、説明いたします。
現在、経理の置かれている状況は深刻だと考えます。
これは、政府がどれだけDX化や脱ハンコを目指すことを国策として提示したところで、導入が難しい状況を指します。
例えば…
・請求書がそもそも紙で来る、もしくは紙の請求書を郵送しなければならないため出社は必須であること
・請求書に上長の押印がないと社内処理ができないこと
・在宅ワークをしようにも、預金やその他の証憑を持ち帰ることができないため、出社が必須であること
などとなります。あくまで一例です。
上記の問題を、自社開発で解決することは非常に難しいです。
経理業務後の決算申告に与える影響や、その他法令に沿った運用ができているかなど、社内で検討すべき事項は多岐に渡り、経理だけでなく、営業部門からのヒアリング、情報システム部との連携など、非常に労力が掛かることが予想されます。
そのため基本的には、現在数多くあるSaaSビジネスを活用することにあります。
脇坂IT税理士事務所では、マネーフォワード社(以下、MF)を使用します。
数ある会計ソフトの中から、MF社を選ぶ理由としましては、MF社の提供するサービスが経理を大幅に強化できるためです。
これまで私の培ってきた経験から、決算申告、その他あらゆる事項の前後工程に支障のないよう経理業務の改善、仕組みの構築をまずは行うことで
御社の経理(バックオフィス)の負担を軽くしてみせます。
つまり、今までの単純作業をなくす、若しくは、それに掛かっていた労力を減らします。
浮いた時間で、現場の求める詳細な資料を作成したり、経営陣の皆様に役立つKPIを提供したり、予実管理を徹底するなど、経理の方が付加価値業務に専念できるよう支援し、またそのお手伝いをします。
2.ペーパレス社会を実現する、とは?
上記の通り、経理のDX化のためには、ペーパレスが必須となります。
振込業務、見積書・納品書等の作成、稟議決裁、請求書作成、経費精算、契約書管理、会計入力…など、まだまだ紙に頼る部分が多いのが現状です。
これらを解決しなければ、経理はいつまでも完全な在宅ワークができず、また付加価値業務に取り掛かれません。
また従来の紙とハンコに頼り続けていると、紙代とプリンターのリース料、インク代のランニングコストは一生無くなりません。
官公庁への提出書類も、極力紙での提出ではなく、電子申告で終える流れとなることは必須ですので、それに備えて、今から準備を整えておく必要があります。
また、日本政府が令和3年度税制改正の中で、電子帳簿保存法の適用要件の簡素化を盛り込んでおり、これが施行するとより、紙の証憑に頼る必要がなくなります。
脇坂IT税理士事務所では、電子帳簿保存法に準拠した、運用周りの支援をさせていただきます.
余談となりますが
経理とは直接関係ありませんが、紙の使用を無くし、例えば、iPadとApplepencilを使うとか、ワコムのペンタブレットを使うなど、全てデジタルで完結させたりすることも可能だと考えます。
この領域は、まだまだ発展途上でありつつも、「完全に紙の使用をなくす」という最終目標を掲げれば、自ずと、そのために今できることを皆さんが考えるキッカケとなると私は信じております。
3.経理業務の効率化の救世主:Pythonについて
まず、上記のDX化、つまりシステムを導入し、社内の仕組みを構築した後は「部分最適化」という作業が必要です。
システムでは補完できない手作業を、IT化により極限まで減らす流れとなります。
結論から申し上げますと…
⭐️「ボタン一つで仕事を終わらせる仕組みを作る」ことが経理におけるIT化の意味となります。
経理の主要な業務ツールといえば、EXCELです。
関数を駆使することで、手作業を減らすこともできますし
またEXCELにはVBAという標準の言語が搭載されており、これをうまく使い、マクロを組むことで手作業を圧倒的に減らすこともできるでしょう。
ですが、VBAはEXCELでしか通用しない言語のため、汎用性は低く、簡単な作業を効率化しようにも、コードが冗長的になります。
前任の経理担当者が辞めたら、マクロのメンテナンスもできません。
だからと言って、関数だけでガチガチに組むと、一つ数式が崩れたら、そのファイルは機能しなくなります。
そこで出てくるのが、当社のPythonにお任せすることです。
Pythonでできることの詳細はここでは割愛いたしますが、脇坂IT税理士事務所が目指すPythonによる業務効率化の一例は下記の通りです。
・御社のEXCELでの手作業をなくす。
・会計データから総勘定元帳を吐き出し、勘定科目コードなどをキーとして、予実管理表を一気に数値更新する。
・得意先コードを設けて、御社のニーズにあった売上原価一覧を作成します。
・御社の販売管理システムから吐き出したcsv データを加工し、主要なKPI指標を作るお手伝いをする。
など、単なる月次PLの説明には終わらない資料を提供を行います。
ゆくゆくは、機械学習モジュールを用いた中期経営計画資料の作成、スクレイピング技術を用いた最新の情報の取得、Djangoフレームワークを用いたWEBアプリ開発などをやってみたいと考えております。
4.日本における中小企業のIT化の問題点につきまして
IT化、すなわち部分最適化に必要なのは、「あらゆる工程に支障がないことを前提としたIT化」となります。
つまり、例えば経理だけがIT化で楽になったところで、他の部署の負担が増えたり、税理士の行う決算業務に支障が出たり、そもそも運用が法令に準拠していない、などの問題が浮上すれば、それはIT化は失敗となります。
それを経理だけが、全工程を踏まえて調整し、行動することなど不可能であるのに加えて、全ての経理の方がITに詳しいわけでもありません。
そもそも、経理の方は今の業務を回すので手一杯です。
また、本来、税理士がその部分を支援しなければならないはずなのですが、税理士についてもIT化が非常に遅れている業界であり、お客様先の経理支援をできる税理士は極小数です。
また、会社様の経営陣の多くの方は、経理などのバックオフィスは「非生産部門」として極力、予算をかけたくない傾向にあると思われます。
つまり、日本政府がどれだけペーパレス、DX、脱ハンコを掲げたところで、それを推進する人材はおらず、経理のDX化、IT化の停滞スパイラルだけが続いている状況です。
脇坂IT税理士事務所では、まずお客様の現状をヒアリングし、DX化すべき事項と、IT化できる事項を洗い出します。
その上で、顧問契約成立初期段階では、御社の経理回りを整備することに注力させていただきます。
そこで、仕組みを構築し終えるということは、御社の経理も楽になりますし、また税理士側である私も楽となり、非常にWIN-WINの関係となります。
料金体系をご覧になっていただくとお分かりかと思いますが、月額顧問料金が安い理由は、決して「安かろう、悪かろう」ではございません。
初期段階で、仕組みを作る時に料金を頂戴いたしますが、仕組み構築後は、私にも月次作業に掛かる工数が発生しませんから、この料金でも可能ということです。
その分、訪問形式の対面回数は減らしますが、月次監査もMFクラウド会計で行い、また月次報告に関してもZoomを使用させていただきます。
5.経理部門が最終的に目指す場所
上記の通り、まずはお客様の経理のDX化とIT化を行います。
その後、御社の経理をさらに強化する事業を構想しております。
第一段階の目標としましては、御社の経理で「税引前当期純利益」まで固めることができるようになること。
第二段階の目標としましては、御社の経理で「現場や、経営陣の方々に役立つ資料を提供できるようになる」こと。
そして、最終段階の目標としましては、御社の経理で「税務知識をつけて、法人税申告書作成までできるようにすること」です。
また、経理のDX化、IT化も導入してそれで終わり、などとは思っておらず、日々ブラッシュアップだと考えております。
そのためには、私ももっと税務会計、Pythonを極めたり、更に最新のSaaSビジネスについて理解し、お客様に還元できるようにいたします。
6.税理士とお客様の理想の関係について
一番は、お客様に「メリットを感じていただける」ようにしたいと考えております。
税理士のサービスは、無形部分が多いため、単なる月次の報告と、決算資料作成では、お客様の不満が芽生えるのはもっともです。
「お茶を飲みに来たのか!?」と中にはお怒りの方もいらっしゃるかもしれません。
よって、脇坂IT税理士事務所では、常に「Give & Take」ではなく、「Give &Give &Give!」の精神で事業を行います。
お客様、とりわけ社長様の心の支えとなるためには、単なる話し相手ではなく
目に見えて分かるメリットを提示し、それを実現することだと考えております。
よって、まずはお互いがより機動的になるためには、経理のDX化、IT化が不可欠です。
そうして、余った時間を以ってして、さらにその先の未来を考えられるような存在になれるよう尽力いたします。
よろしくお願いいたします。
- その他記事
Copyright © 2025 四条烏丸法律事務所 All rights reserved.